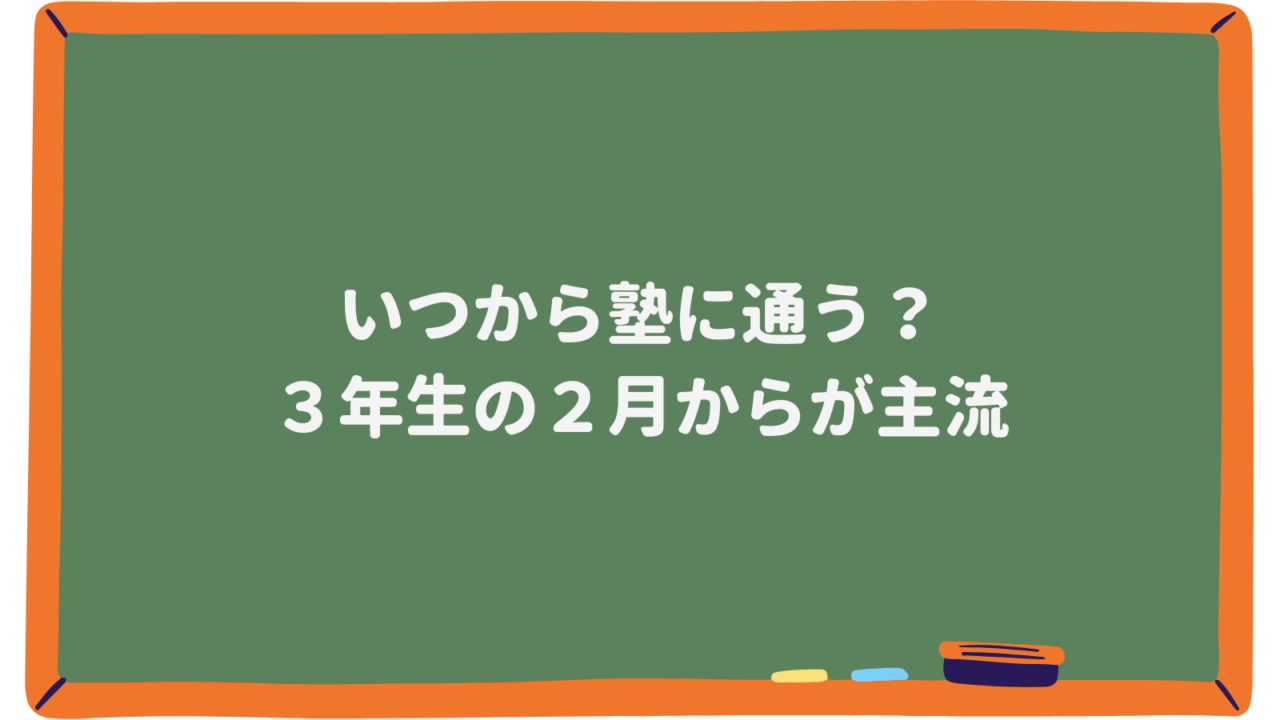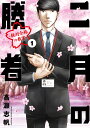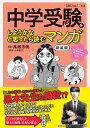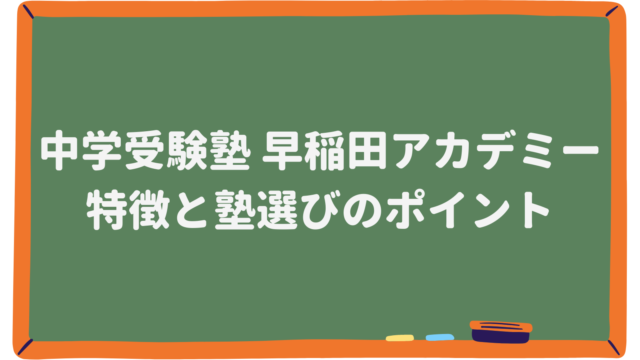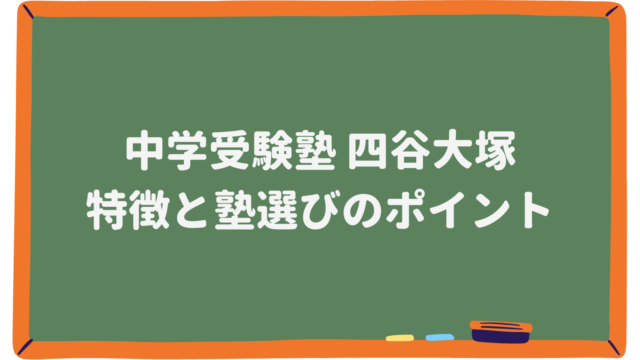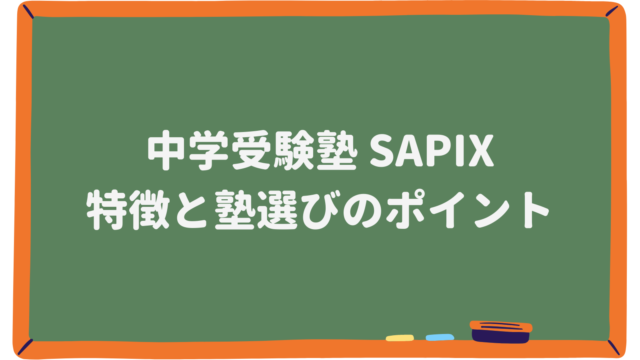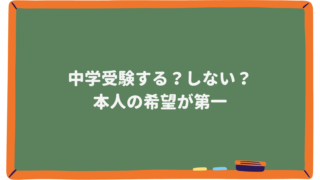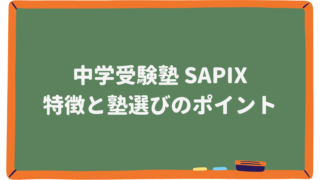こんにちは、そしてこんばんは、ぽこたろうです。
中学受験をしたいけれど、いつから塾に通ったら良いのか?
お悩みのご家庭もいらっしゃるのではないでしょうか。
調べるまではそう思っていました。
実は、3年生の2月から塾通いを始めるのが主流のようです。
塾通いを始めることを入塾と言います(塾に入る、そのままですね)
多くの受験生は、受験の3年も前に入塾し、受験勉強を始めているようです。
こんなに早くから塾に通っているんですね。
今回は、3年生の2月から塾に通い始める理由についてまとめていきたいと思います。
塾通い(入塾)考えるにあたって、参考にしていただけると嬉しいです。
3年間で受験勉強のスケジュールが組まれている
なぜ3年生の2月に入塾するのでしょうか。
- 入試が6年生の1月や2月に行われる
- 3年生の2月から、入試日までの3年間のカリキュラムが組まれている
というのが大きな理由です。
4年生になってから入塾したのでは、入試日まで3年を切ってしまいますし、6年生になってから入塾したのでは、1年を切ってしまっているんですね。
また、中学受験の入試問題は小学校の教科書レベルを遥かに超える難易度で出題されるため、膨大な量の受験対策をする必要があります。
そのため、1年間では対策をする時間が圧倒的に足りず、3年かけて対策をしていく必要があるようです。
それでは、大まかに3年間のスケジュールを見ていきましょう。
| 学年 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 2月 | 通年 |
| 3年生 | 入塾対策 | 入塾テスト | 入塾 | |||
| 4年生 | 春季講習 | 夏期講習 | 冬季講習 | 週2〜3授業・テスト | ||
| 5年生 | 春季講習 | 夏期講習 | 冬季講習 | 週3〜4授業・テスト | ||
| 6年生 | 春季講習 GW講習 | 夏期講習 | 冬季講習 正月講習 | 週4〜5授業・テスト |
4年生から週2〜3の授業・テストが始まり、長期休暇には講習が予定されています。
5年生・6年生になると塾の回数が増えていきます。
6年生では、GWや正月に講習が入り、本格的に受験対策を行います。
- 4年生:勉強に慣れる。基礎力の定着
- 5年生:6年生までの単元を終える
- 6年生:総復習。入試に向けた演習問題。志望校別対策
このように、3年間の計画的なカリキュラムにより、受検対策がなされています。
昔は5年生や6年生になってから入塾しても問題ないとされていましたが、現在は昔に比べて入試問題が難化したり出題範囲が広くなったりしている影響により、3年間での対策が必要となっているようです。
入塾が遅れるとどうなる?
それでは、入塾が遅れるとどうなるのでしょうか。
5年生から入塾して受験勉強を始めた場合
4年生から塾通いをしている子たちと比較すると、基礎力の定着が遅くなります。
また、塾のカリキュラムとしても、基礎力が定着している前提で授業が進むことがありますので、授業内容が難しいと感じることになるかもしれません。
その巻き返しのため、塾の予習をやる必要があります。
6年生から入塾して受験勉強を始めた場合
多くの塾では6年生までの単元を終えて、総復習や入試に向けた演習問題に取り掛かっていますので、未習単元がある状況で塾通いが始まってしまいます。
4年生から塾通いをしている子たちと比較すると、あまりに習学状況が違うため、戸惑いや混乱が生じるかもしれません。
そのような状況の中で、基礎力の定着から始める必要がありますので、塾と相談しながら独自の対策を講じていく必要があります。
入塾が遅くなっても問題ない?
「問題ない」と言い切るのは難しいでしょう。
しかし、5年生からであれば、入塾の遅れを取り戻す取り組みがあるようです。
頑張って遅れを取り戻そうと取り組んでも、現実的な志望校は主に中堅校になると思われます。難関校を目指すのであれば、3年生2月から入塾した方がよいでしょう。
入塾の遅れを取り戻す取り組みとは、塾のテキストに加えて市販のテキストを併用することです。
予習・復習の際に、塾のテキストに加えて市販のテキストで補うことが効果的のようです。(5年生であれば、3年生用・4年生用の市販のテキストを利用する等)
また、予習・復習以外の用途として、塾で分からない用語や難しいと感じた問題が出てきたときに、市販のテキストを使って調べて問題を解く、というような取り組みで理解を補うことができます。
以下のテキストがオススメです。
- 四谷大塚 「予習シリーズ」
- 増進堂・受験研究社 「自由自在」
「予習シリーズ」は、大手塾の四谷大塚が執筆しているテキストで、内容が細かく丁寧、予習・復習に最適、と人気です。
四谷大塚の塾生でなくても購入できるのもよいですね。四谷大塚のHPから購入できます。
「自由自在」は、1953年に初版が発行されてから2400万部を発行している人気のテキストです。
基礎から難関校受験レベルまで幅広い内容が取り扱われていたり、図表や写真が多く載せられていたりと、分かりやすくするための工夫がされています。
一方で、6年生から入塾では、市販のテキストを使った取り組みでも基礎力の定着までが限界だと思われます。
なので、カリキュラムが決まっている大手塾ではなく、少人数の塾や個別指導等で、子どもの習学状況が理解度の状況に合わせて柔軟に対応できるようにした方がよいでしょう。
3年生の2月から塾通いを始めるのが主流
3年間の計画的なカリキュラムで受験対策がなされてているので、中学受験をするのであれば、3年生の2月から入塾した方が望ましく、多くの受験生にとってそれが主流のようです。
4年生は基礎力の定着が主な目的といえども、4年生の1年間、塾通いをして受験対策をするのとしないのとでは、5年生以降での習学状況や勉強の取り組み内容で大きな違いが表れます。
なお、どういう塾があるのかについては以下の記事をご覧ください。
四大塾であるSAPIX・日能研・四谷大塚・早稲田アカデミーについての紹介、個別指導・家庭教師・通信教育の特徴についてまとめています。
以上、いつから塾に通う?3年生の2月からが主流、についてでした。
中学受験の長い旅路に、少しでも参考になれば嬉しいです。
最後までご覧いただきありがとうございました。
それでは、また。
参考:中学受験でオススメの本
さいごに参考として、中学受験でオススメの本を紹介します。
どれも一読しておきたい有用な本です。
中学受験 基本のキ!
「中学受験 基本のキ!」は、「なぜ中学受験をするのか?」という最も大事なところから、塾選び・学校選び・学年別の過ごし方・勉強方法等、中学受験における基本的な情報がギッシリ詰まっています。
これから中学受験を考えるご家庭も、中学受験を始めているけどまだ読んでいないご家庭も、読んでおいて損はないでしょう。
中学受験は親が9割
「中学受験は親が9割」は、中学受験の合否を決める9割が親にかかっているという意味で、家族の協力無しには中学受験は成功しないということを表しています。本書では中学受験の最新事情から、親がやるべき習慣・やってはいけない習慣、合格に向けて親が取り組むことについてまとめられています。
「中学受験 基本のキ!」と同様、読んでおいて損はない1冊です。
二月の勝者 -絶対合格の教室ー
「二月の勝者 -絶対合格の教室ー」は、ドラマ化もされている人気漫画で、中学受験の世界がリアルに描かれています。物語の展開に合わせた心情が、受験する子ども目線だけではなく大人(保護者)の目線でも描かれており、親の立場として感じるであろう気持ち(期待・迷い・不安・葛藤)をリアルに感じることができます。
漫画なので、親子で読んで気持ちを共有することもできますね。中学受験がどういうものかを知るには、オススメの漫画です。
中学受験をしようかなと思ったら読むマンガ
「中学受験をしようかなと思ったら読むマンガ」は、中学受験の始めから合格後までをシミュレーションできる漫画です。「中学受験のウソ?ホント?」と題したコラムも書かれており、中学受験を始めるにあたって気になるポイントも押さえることができます。
漫画でかつ1冊で完結しており気軽に読むことができますので、ます最初に読んでみるのがよいでしょう。